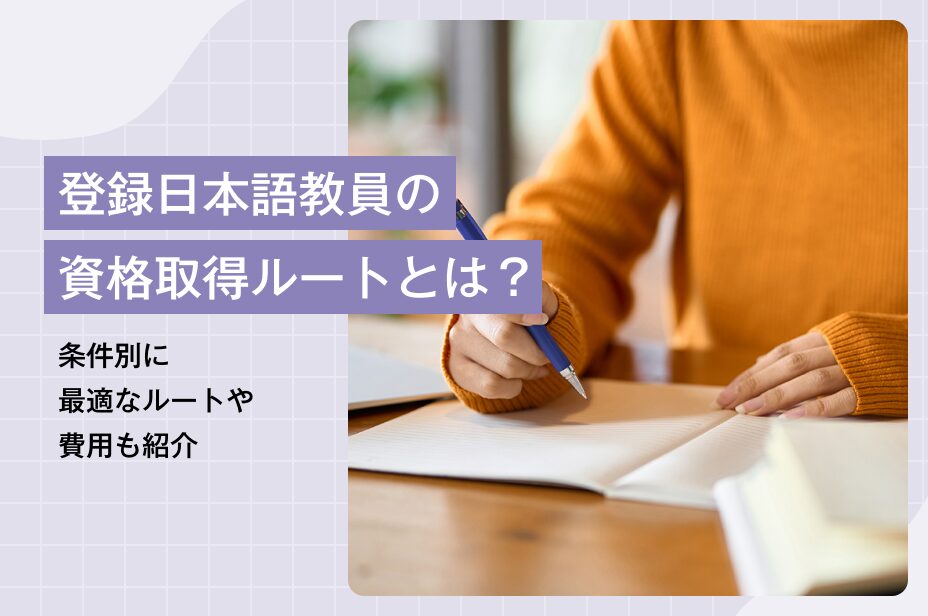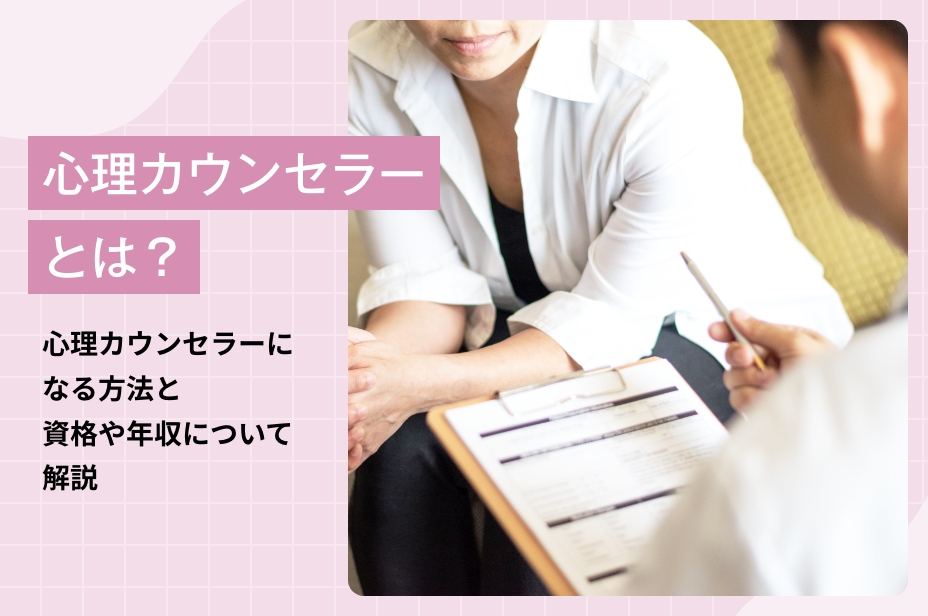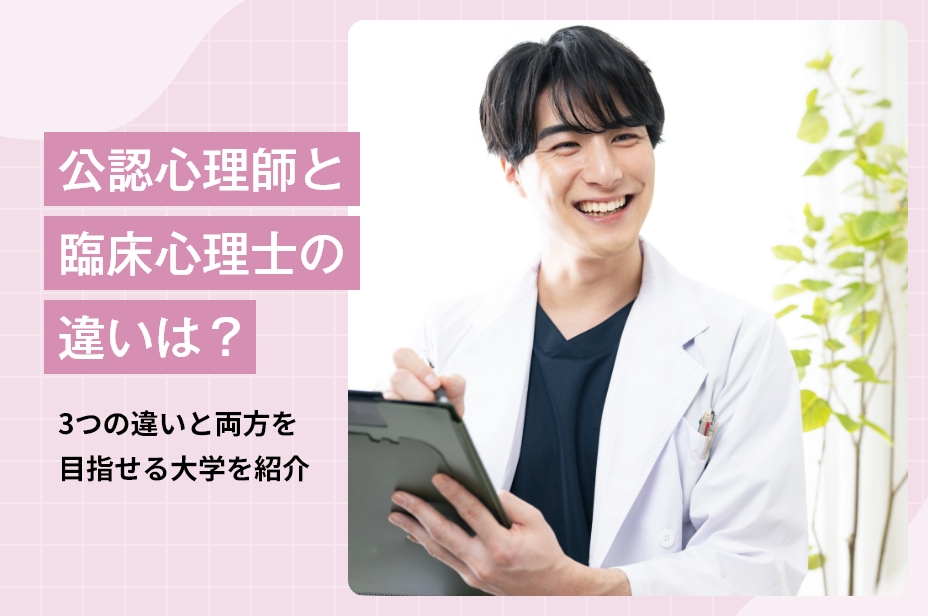いつでも通信
- 資格
- 日本語教員
日本語教師の民間資格・国家資格の取得難易度と合格率について解説
※2024年10月30日現在の内容です
日本語教師になるための資格には、民間資格と国家資格があります。それぞれの資格は、大学・大学院、養成講座に通って取得する方法と、試験に合格することによって取得する方法があります。
時間や経済的な理由などで学校に通うことが難しく、試験合格をめざすほうが都合のよい人もいることでしょう。実際に、独学で試験に合格して日本語教師として活躍している人も多くいます。そこで、この記事では、民間資格「日本語教育能力検定試験」と国家資格「登録日本語教員」を取得する場合の難易度について解説します。
日本語教師の資格を取得するには?

日本語教師になるには、文部科学省の「日本語教育機関の告示基準第1条第1項第13号」によって定められている、次の4つの資格のいずれかに該当する必要があります。
- 大学または大学院にて日本語教育に関する教育課程を修了。
- 「日本語教育能力検定試験」に合格。
- 「420時間日本語教師養成講座」を修了。
- 登録日本語教員資格の取得。
上記の1〜3は、2023年まで一般的だった民間資格で、2024年4月に一部改訂されてから、4の国家資格「登録日本語教員」が加わりました。
2024年7月現在では、日本語教師の求人の条件には、1〜3の資格のいずれかに該当することが必須条件とされていることが多いのですが、今後は国家資格「登録日本語教員」の保有を必須とする求人も出てくるものと予想されています。
プライベートレッスンやボランティア、海外就労などの法務省告示校以外の場所で日本語を教えるのであれば、制度上は、いずれの資格がなくても日本語教師として教えることはできます。しかし、国内の日本語学校では資格を有していることが条件であることが多く、法務省告示の日本語教育機関では、資格は必須です。また、先述の通り、「認定日本語教育機関」で日本語教師として働く場合には、国家資格である「登録日本語教員」が必要です。
現実的に、日本語についての知識や指導技術が身についていなくては、正しい日本語を教えることは難しいでしょう。日本語学校や日本語教育機関の採用試験で重視されるのは、日本語の指導力です。以上の点から、日本語教師をめざすには、やはり資格取得は不可欠と言えます。
上記の1と3は、大学・大学院の課程や養成講座を修了すれば、資格を得ることができますが、2と4は、それぞれの試験に合格しなければ資格取得はできません。そこで、ここからは日本語教育能力検定試験と登録日本語教員試験の難易度について解説します。
日本語教師について詳しく以下の記事をご確認ください。
日本語教師の民間資格「日本語教育能力検定試験」の難易度や合格率は?
日本語教育能力検定試験は、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)によって年に1回、10月に実施されています。
年齢や学歴に制限はなく、誰でも受験可能であることが特長で、合格率は直近10年間では25~30%程度。難易度は高めと言えるでしょう。
出題範囲は下の表の通りです(令和4年度より)。ただし、すべての範囲が出題されるとは限りません。
横スクロールできます
| 区分 | 主要項目 | |
|---|---|---|
| 社会・文化・地域 | ①世界と日本 | (1) 世界と日本の社会と文化 |
| ②異文化接触 | (2) 日本の在留外国人施策 | |
| (3) 多文化共生 (地域社会における共生) | ||
| ③日本語教育の歴史と現状 | (4) 日本語教育史 | |
| (5) 言語政策 | ||
| (6) 日本語の試験 | ||
| (7) 世界と日本の日本語教育事情 | ||
| 言語と社会 | ④言語と社会の関係 | (8) 社会言語学 |
| (9) 言語政策と「ことば」 | ||
| ⑤言語使用と社会 | (10) コミュニケーションストラテジー | |
| (11) 待遇・敬意表現 | ||
| (12) 言語・非言語行動 | ||
| ⑥異文化コミュニケーションと社会 | (13) 多文化・多言語主義 | |
| 言語と心理 | ⑦言語理解の過程 | (14) 談話理解 |
| (15) 言語学習 | ||
| ⑧言語習得・発達 | (16) 習得過程 (第一言語・第二言語) | |
| (17) 学習ストラテジー | ||
| ⑨異文化理解と心理 | (18) 異文化受容・適応 | |
| (19) 日本語の学習・教育の情意的側面 | ||
| 言語と教育 | ⑩言語教育法・実習 | (20) 日本語教師の資質・能力 |
| (21) 日本語教育プログラムの理解と実践 | ||
| (22) 教室・言語環境の設定 | ||
| (23) コースデザイン | ||
| (24) 教授法 | ||
| (25) 教材分析・作成・開発 | ||
| (26) 評価法 | ||
| (27) 授業計画 | ||
| (28) 教育実習 | ||
| (29) 中間言語分析 | ||
| (30) 授業分析・自己点検能力 | ||
| (31) 目的・対象別日本語教育法 | ||
| ⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 | (32) 異文化間教育 | |
| (33) 異文化コミュニケーション | ||
| (34) コミュニケーション教育 | ||
| ⑫言語教育と情報 | (35) 日本語教育とICT | |
| (36) 著作権 | ||
| 言語 | ⑬言語の構造一般 | (37) 一般言語学 |
| (38) 対照言語学 | ||
| ⑭日本語の構造 | (39) 日本語教育のための日本語分析 | |
| (40) 日本語教育のための音韻・音声体系 | ||
| (41) 日本語教育のための文字と表記 | ||
| (42) 日本語教育のための形態・語彙体系 | ||
| (43) 日本語教育のための文法体系 | ||
| (44) 日本語教育のための意味体系 | ||
| (45) 日本語教育のための語用論的規範 | ||
| ⑮言語研究 | ||
| ⑯コミュニケーション能力 | (46) 受容・理解能力 | |
| (47) 言語運用能力 | ||
| (48) 社会文化能力 | ||
| (49) 対人関係能力 | ||
| (50) 異文化調整能力 | ||
※参照:『日本語教育能力検定試験 出題範囲等』(公益財団法人日本国際教育支援協会ホームページ・https://www.jees.or.jp/jltct/range.htm
試験は240点満点で、「試験Ⅰ」「試験Ⅱ」「試験Ⅲ」から構成されています。
試験Ⅰは、解答時間90分、配点100点。
原則として、出題範囲の区分ごとの設問により、日本語教育の実践につながる基礎的な知識を測定します。
試験Ⅱは、解答時間30分、配点40点。
試験Ⅰで求められる「基礎的な知識」および試験Ⅲで求められる「基礎的な問題解決能力」について、音声を媒体とした出題形式で測定します。
試験Ⅲは、解答時間120分、配点100点。
原則として出題範囲の区分横断的な設問により、熟練した日本語教員の有する現場対応能力につながる基礎的な問題解決能力を測定します。
日本語教育能力検定試験の合格基準は明らかにされていません。しかし、一般的に資格試験は165点前後が合格ラインとされており、得点が約7割以上であれば合格とされているのが参考となるでしょう。
直近10年間の合格率は25~30%
年齢や学歴に制限はなく、誰でも受験可能であることが特長で、合格率は直近10年間では25~30%程度。難易度は高めと言えるでしょう。
しかし、試験が開始された1987年(昭和62年)から2007年(平成19年)までの20年間の合格率は20%程度でしたので、合格率は徐々に上がってきています。
過去の実施状況と合格率
第1回(昭和62年度)から第37回(令和5年度)までの実施状況と合格率は下の表の通りです。合格率は第1回の昭和62年度の19.6%から少しずつ上昇の傾向にあり、令和4年度には30%を超えています。
横スクロールできます
| 実施回 | 実施年度 | 応募者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 実施地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 昭和62年度 | 5,837 | 4,758 | 935 | 19.6 | 1 |
| 第2回 | 昭和63年度 | 5,794 | 4,597 | 827 | 17.9 | 2 |
| 第3回 | 平成元年度 | 6,783 | 5,405 | 999 | 18.4 | 2 |
| 第4回 | 平成2年度 | 6,367 | 5,143 | 908 | 17.6 | 3 |
| 第5回 | 平成3年度 | 7,815 | 6,224 | 1,153 | 18.5 | 3 |
| 第6回 | 平成4年度 | 8,723 | 6,846 | 1,272 | 18.5 | 3 |
| 第7回 | 平成5年度 | 8,673 | 6,792 | 1,224 | 18.0 | 3 |
| 第8回 | 平成6年度 | 8,282 | 6,153 | 1,125 | 18.2 | 3 |
| 第9回 | 平成7年度 | 7,614 | 5,911 | 1,107 | 18.7 | 3 |
| 第10回 | 平成8年度 | 7,755 | 5,986 | 1,088 | 18.1 | 4 |
| 第11回 | 平成9年度 | 7,624 | 5,824 | 1,077 | 18.4 | 4 |
| 第12回 | 平成10年度 | 6,906 | 5,272 | 1,008 | 20.6 | 4 |
| 第13回 | 平成11年度 | 7,526 | 5,729 | 1,091 | 19.0 | 4 |
| 第14回 | 平成12年度 | 7,809 | 5,858 | 1,077 | 18.3 | 4 |
| 第15回 | 平成13年度 | 7,319 | 5,549 | 1,008 | 18.1 | 4 |
| 第16回 | 平成14年度 | 7,989 | 6,154 | 1,171 | 19.0 | 4 |
| 第17回 | 平成15年度 | 8,103 | 6,426 | 1,235 | 19.2 | 4 |
| 第18回 | 平成16年度 | 8,401 | 6,715 | 1,220 | 18.1 | 5 |
| 第19回 | 平成17年度 | 7,231 | 5,958 | 1,155 | 19.3 | 5 |
| 第20回 | 平成18年度 | 6,374 | 5,317 | 1,126 | 21.1 | 6 |
| 第21回 | 平成19年度 | 5,837 | 4,793 | 981 | 20.4 | 6 |
| 第22回 | 平成20年度 | 5,773 | 4,767 | 1,020 | 21.4 | 6 |
| 第23回 | 平成21年度 | 6,277 | 5,203 | 1,215 | 23.3 | 6 |
| 第24回 | 平成22年度 | 6,823 | 5,616 | 1,197 | 21.3 | 7 |
| 第25回 | 平成23年度 | 7,034 | 5,769 | 1,527 | 26.4 | 7 |
| 第26回 | 平成24年度 | 5,877 | 4,829 | 1,109 | 22.9 | 7 |
| 第27回 | 平成25年度 | 5,439 | 4,402 | 1,001 | 22.7 | 7 |
| 第28回 | 平成26年度 | 5,436 | 4,389 | 1,027 | 23.4 | 7 |
| 第29回 | 平成27年度 | 5,920 | 4,754 | 1,086 | 22.8 | 7 |
| 第30回 | 平成28年度 | 6,167 | 4,934 | 1,231 | 24.9 | 7 |
| 第31回 | 平成29年度 | 7,331 | 5,767 | 1,463 | 25.3 | 7 |
| 第32回 | 平成30年度 | 8,586 | 6,841 | 1,937 | 28.3 | 7 |
| 第33回 | 令和元年度 | 11,699 | 9,426 | 2,659 | 28.2 | 7 |
| 第34回 | 令和2年度 | 11,316 | 9,084 | 2,613 | 28.7 | 7 |
| 第35回 | 令和3年度 | 10,216 | 8,301 | 2,465 | 29.7 | 7 |
| 第36回 | 令和4年度 | 8,785 | 7,076 | 2,182 | 30.8 | 7 |
| 第37回 | 令和5年度 | 10,170 | 8,249 | 2,542 | 30.8 | 7 |
※「受験者数(人)」は科目受験者を含みます。「合格率(%)」は、合格者数を受験者数で割った数値です(小数点2位以下切り捨て)。
※参照:『令和5年度 日本語教育能力検定試験 結果の概要』(公益財団法人 日本国際教育支援協会ホームページ・https://www.jees.or.jp/jltct/pdf/R5kekkanogaiyo.pdf)
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」取得の難易度や合格率とは?

2023年5月26日、日本語教師の国家資格化に関する法案「日本語教育機関認定法」が成立。2024年4月から施行され、日本語教師の国家資格「登録日本語教員」が誕生しました。
「登録日本語教員」とは、「認定日本語教育機関」で日本語教師として働く場合に取得しなければならない資格です。認定日本語教育機関とは、在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関のことで、現在の法務省告示校にあたります。登録日本語教員制度についての概要は、2024年10月に公開されました。登録日本語教員になるために必要な登録申請等の手続きについては、下記ホームページで必要に応じて随時更新されています。
※参照:『登録日本語教員の 登録申請の手引き』(文部科学省ホームページ・https://www.mext.go.jp/content/20241025-mxt_nihongo02-000034832_5.pdf
認定日本語教育機関で働きたい人は、「登録日本語教員」の資格取得がおすすめです。ただし、ビザを発給しない語学学校や日本語教室、企業派遣などの日本語教育機関、企業、オンラインなどで日本語教師をする場合は、「登録日本語教員」である必要はありません。
資格を取得するには、主に「2種類の養成機関ルート」、「試験ルート」、「経過措置Cルート」の三つのルートがあります。
なお、すでに日本語教師の資格を取得して、日本語教師として働いている方には「経過措置D~Fルート」が用意されています。
三つのルートを解説すると、まず「養成機関に通うルート」は、定められた養成機関に通い、必要な教育課程を修了して、登録日本語教員資格を取得する方法です。
このルートには二通りあり、一つは、「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」の登録を受けた機関で課程を修了する方法です。この場合、実践研修は養成機関の課程の中に含まれるので、基礎試験は免除されます。つまり、課程を修了後は、応用試験に合格すれば日本語教員資格を得られます。
もう一つは、「登録実践研修機関」の登録を受けておらず「登録日本語教員養成機関」の登録を受けた機関で課程を修了する場合のルートです。この場合、基礎試験は免除されますが、応用試験に合格した上で、登録実践研修機関で実務研修を受講し、修了すると登録日本語教員になれます。
次に、「試験ルート」は養成機関に通わず、独学で基礎試験と応用試験を受験する方法です。基礎試験と応用試験に合格した後、登録実践研修機関での実践研修を修了すると登録日本教員の資格を取得できます。
三つ目の「経過措置Cルート」は、「必須の教育内容50項目」の実施に対応する日本語教員養成機関で課程を修了する方法です。このルートで登録日本語教員の資格を取得するためには、大学卒業(学士)以上の資格が必要です。
基礎試験と実践研修は免除となるので、日本語教員養成機関で課程を修了後、応用試験に合格すれば、登録日本語教員になれます。
以上のように、登録日本語教員になるには養成講座の受講に加え、「日本語教員試験」の合格も必須であるため、「日本語教育能力検定試験」よりも難易度は高いと言えるでしょう。
出題範囲は、基礎試験は日本語教育を行うために必要となる基礎的な知識および技能を区分ごとに出題され、応用試験は基礎的な知識および技能を活用した問題解決能力を測定することを目的に教育実践と関連して出題されます。
応用試験の一部は聴解問題とし、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を用いて、より実際の教育実践に即した問題が出題され、問題解決能力や現場対応能力等が判定されます。
基礎試験の出題範囲は下の表の通りです。
横スクロールできます
| 全体目標 | 一般目標 | 必須の教育内容 | 基礎試験おおむねの出題割合(※) |
|---|---|---|---|
| 社会・文化・地域 | ①世界と日本 | <1>世界と日本の社会と文化 | 約1~2割 |
| ②異文化接触 | <2>日本の在留外国人施策 <3>多文化共生(地域社会における共生) |
||
| ③日本語教育の歴史と現状 | <4>日本語教育史 <5>言語政策 <6>日本語の試験 <7>世界と日本の日本語教育事情 |
||
| 言語と社会 | ④言語と社会の関係 | <8>社会言語学 <9>言語政策と「ことば」 |
約1割 |
| ⑤言語使用と社会 | <10>コミュニケーションストラテジー <11>待遇・敬意表現 <12>言語・非言語行動 |
||
| ⑥異文化コミュニケーションと社会 | <13>多文化・多言語主義 | ||
| 言語と心理 | ⑦言語理解の過程 | <14>談話理解 <15>言語学習 |
約1割 |
| ⑧言語習得・発達 | <16>習得過程(第一言語・第二言語) <17>学習ストラテジー |
||
| ⑨異文化理解と心理 | <18>異文化受容・適応 <19>日本語の学習・教育の情意的側面 |
||
| 言語と教育 | ⑩言語教育法・実習 | <20>日本語教師の資質・能力 <21>日本語教育プログラムの理解と実践 <22>教室・言語環境の設定 <23>コースデザイン <24>教授法 <25>教材分析・作成・開発 <26>評価法 <27>授業計画 <29>中間言語分析 <30>授業分析・自己点検能力 <31>目的・対象別日本語教育法 |
約3~4割 |
| ⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 | <32>異文化間教育 <33>異文化コミュニケーション <34>コミュニケーション教育 |
||
| ⑫言語教育と情報 | <35>日本語教育と ICT <36>著作権 |
||
| 言語 | ⑬言語の構造一般 | <37>一般言語学 <38>対照言語学 |
約3割 |
| ⑭日本語の構造 | <39>日本語教育のための日本語分析 <40>日本語教育のための音韻・音声体系 <41>日本語教育のための文字と表記 <42>日本語教育のための形態・語彙体系 <43>日本語教育のための文法体系 <44>日本語教育のための意味体系 <45>日本語教育のための語用論的規範 |
||
| ⑮コミュニケーション能力 | <46>受容・理解能力 <47>言語運用能力 <48>社会文化能力 <49>対人関係能力 <50>異文化調整能力 |
※応用試験は複数の区分にまたがる横断的な設問であるため、出題割合は示されていません。
第1回の日本語教員試験は、2024年(令和6年)11月に実施されるため、合格発表は同年12月20日の予定です。そのため、現時点では合格率については不明です。
ただし、合格基準は、「令和6年度日本語教員試験実施要項」によれば、基礎試験は「必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること」、応用試験は「総合得点で6割の得点があること」とされています。
合格基準
横スクロールできます
| 基礎試験 | 必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること。 |
|---|---|
| 応用試験 | 総合得点で6割の得点があること。 |
以上のように、基礎試験の出題範囲の広さと、「8割の得点があること」が合格基準であることから、試験に合格して国家資格「登録日本語教員」になるのは、かなり難易度が高いことが予想されます。
その点、養成機関に通うルートであれば、基礎試験が免除されるので、資格取得率が上がるかもしれません。さらに、登録実践研修機関も兼ねた登録日本語教員養成機関であれば、実践研修も一体的に行えるため、より資格が取れる道は開かれているかもしれません。
※参照:『令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題』(文部科学省ホームーページ・https://www.mext.go.jp/content/20240524-mxt_nihongo02-000036014_2.pdf)
※日本語教師の国家資格について詳しくは以下の記事をご確認ください。
大手前大学通信教育部で日本語教師(登録日本語教員)をめざす
大手前大学通信教育部は、「登録日本語教員資格の取得」で説明した「経過措置適用対象」となっている大学なので、「経過措置Cルート」で登録日本語教員をめざすことができます。
また、大手前大学は文部科学大臣の登録を受けた「実践研修と養成課程を一体的に実施する機関」をめざしています。※1
大手前大学で登録日本語教員をめざすメリットは、大学卒業資格も取得できることで、日本語教師としての活躍のフィールドが広がること、日本語教員養成課程のカリキュラムに加えて、170科目から興味ある科目を学べるので、日本語教師になってから役立つ教養・知識が習得できること、さらには、教育実習以外は24時間対応のオンライン学修で修了できることなどです。※2
※1 文部科学省における審査の結果、予定した実践研修(又は養成課程)が開設できない可能性があります。
※2 大手前大学で登録日本語教員の資格を取得する場合について、詳しくは以下ページをご確認ください。
海外移住への第一歩として資格取得をめざしたHさん

日本語教員の資格を取得。
新たなキャリアのスタートに期待を膨らませています。
将来ベトナムに移住し民宿を経営したいと考えています。その実現のための第一歩として日本語教員の資格取得を決意。また就労ビザ取得のためには学士号が必要なので、日本語教員と学士号の両方をめざせる大手前大学を選びました。同時期に転職と進学が重なったのですが、オンライン受講が中心なので仕事と両立できると判断。動画授業の倍速視聴や科目試験のオンライン受験など、思っていた以上の学びやすさがあり、挫折することなく継続して勉強できたことは大きな自信になりました。日本語教育実習では、5日間みっちりと実践的な指導経験を積むことができました。特にティーチャートークといって、日本語学習初級者が理解しやすいような話し方や言葉選びを訓練できたことがよかったです。授業づくりも経験し、バックパッカーでの体験を取り入れた内容には生徒から「おもしろかった」と感想がもらえ、初めて教える喜びを噛み締めることができました。卒業後、日本語学校に内定をもらえたので、新たなキャリアのスタートに期待を膨らませています。
大卒資格とのW資格取得を目標に入学したTさんのケース

日本語教員としてのキャリアアップをめざし、
専門的に学べる通信制大学へ。
非常勤講師として日本語教員のキャリアをスタートさせるも、制度の見直しにより国内外で活躍するには大卒資格が欠かせないことを知りました。卒業率の高さなどに注目して大学を検討していたときに、先輩講師から「日本語教育に特化した大学ある」と紹介されたのが大手前大学でした。スクーリング科目を履修することなく、オンラインでの学修だけで卒業できることも入学の決め手になりました。印象的だったのは、先生方の指導方法でした。話し方や間のとり方、教材など学修意欲を高めるためのさまざまな工夫があり、一方的に教わるのではなく、学生が能動的に考え、理解が深まる授業でした。自分が体験した学修を通して発見した学ぶ楽しさを日本語教員の指導にぜひ活かしたいと思います。
仕事や家事と両立して卒業したWさんのケース

“学びたい、知りたい”と思ったら行動する!
大手前の学びが生涯学習の基盤になりました。
ドイツ人の夫と生活をしていると、「気を付けてね」の「ね」ってどういう意味といった、日本語に関する質問をよく受けます。私自身も答えに詰まることが多く、自分で調べていくうちに、日本語教育に興味を持ちました。大手前大学を選んだ理由は、自分のライフスタイルに合わせて学修できるeラーニングや、専攻に関係なく興味がある分野を学ぶことのできる履修制度に魅力を感じたからです。実際に履修してみると、教科の達成度がパーセンテージで表示されるため状況を把握しやすく、仕事や家事と両立しながらでも学修計画通りに進めることができました。また、日本語教育能力検定試験対策ができる科目もあり、無事に合格することができました。行き詰まることもありましたが、熱心な指導と細やかなサポートのおかげで卒業時には優等賞を受賞することができました。“知りたい”という気持ちと、好奇心を大切にして、一生涯、学び続けたいと思います。将来は、日本語や食文化を通して日本の魅力を伝えていきたいです。