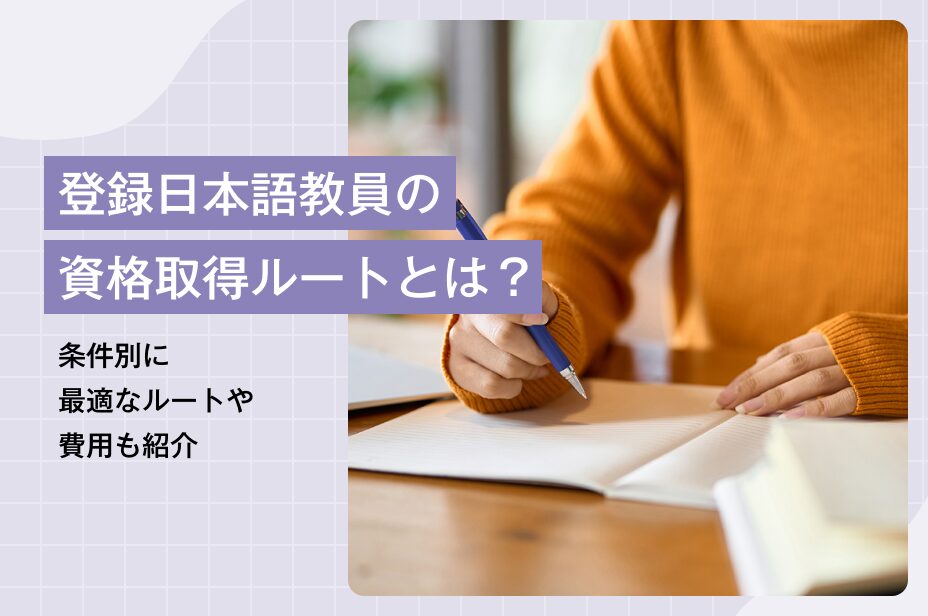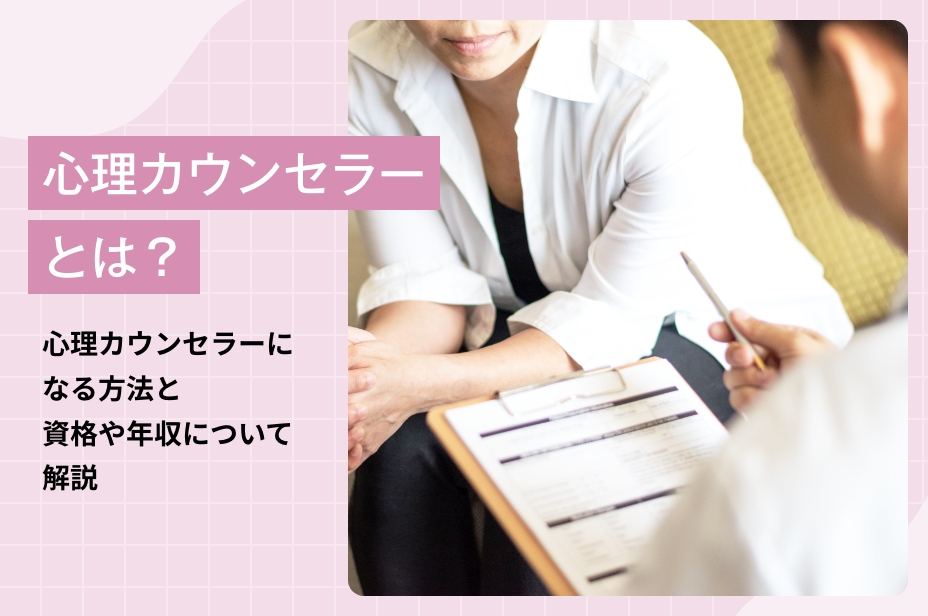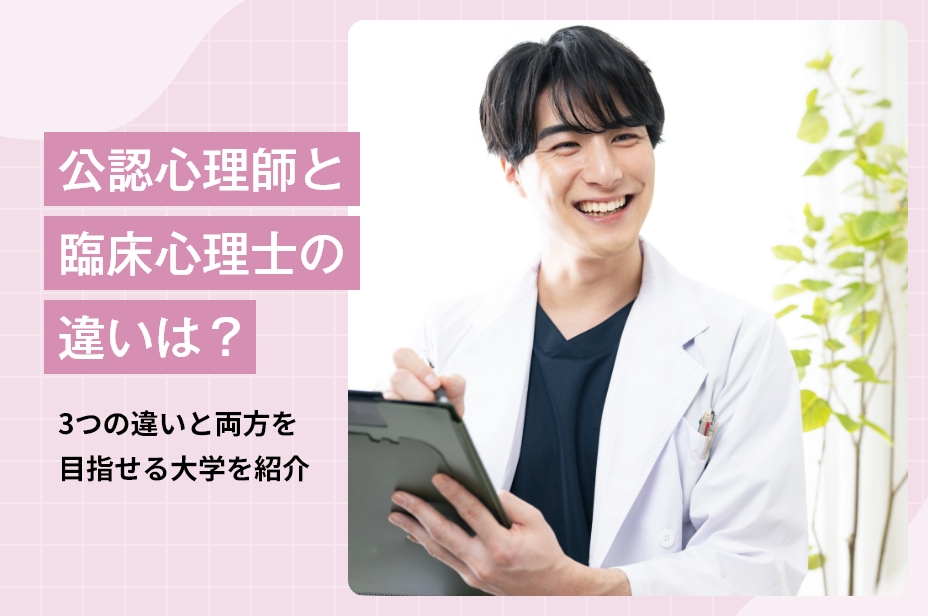いつでも通信
- 資格
- 日本語教員
日本語教師になるための資格取得費用はいくら?登録日本語教員の費用についても解説

※2024年10月30日現在の内容です
日本語教師になるための方法は何通りもあり、それぞれかかる費用は異なります。大学で課程を修める方法であれば数百万円かかりますし、独学であれば検定料の数万円で済みます。また、同じ養成講座に通うにしても、高いところから割安なところまであるので、通いやすさや講座の質なども見極めながらの検討が必要でしょう。
しかし、費用がただ安ければいいわけではなく、大切なのは日本語教師になるという目的を達成することです。目的を明確にするとともに費用とのバランスを考えながら、自分にとってベストな学修方法を選びましょう。ここでは、日本語教師になるための方法ごとにかかる費用の目安と、それを安くできる方法などについても解説します。
- 日本語教師になるための費用は?
- 「420時間日本語教師養成講座」の平均費用
- 「420時間日本語教師養成講座」の費用を抑える方法
- 大学で日本語教育を学ぶ場合
- 「420時間日本語教師養成講座」や大学を選ぶ際のポイント
- まとめ
- 大手前大学 通信教育部で日本語教師(登録日本語教員)をめざす
日本語教師になるための費用は?
「420時間日本語教師養成講座」「日本語教育能力検定試験」「大学で学ぶ」「日本語教員試験」など、日本語教師になる方法はさまざまですが、かかる費用はそれぞれ変わってきます。
いずれにしても、日本語教師をめざすうえで、費用は重要課題です。社会人で働きながら学ぶ人にとっては、通常、大学へ通う費用を捻出するのはたいへんなことでしょう。独学にしても、大学や養成講座に通うほどではありませんが費用はかかります。
授業料や受講料以外にも、交通費やテキスト代、オプション講座などで予想よりも費用がかかってしまう場合もあります。ここでは費用の面にフォーカスして、価格とのバランスも把握しながら、自分に適した日本語教師になる方法を考えてみましょう。また、それぞれの方法について、費用を安く抑える工夫のポイントも解説します。
「420時間日本語教師養成講座」の平均費用
「420時間日本語教師養成講座」を受講する場合、スクールや講座内容によって違いはありますが、だいたいの受講料は40~70万円が相場です。費用には、受講料のほか、入学金や教材費などが含まれているのが一般的です。
また、通学制の場合は交通費の負担も大きく、そのほかにも昼食代などの経費がかかってしまいます。予算内に収めるには、入学前にきちんと調べておく必要があります。
養成講座によっては費用が70万円以上の場合もありますが、受講料が高いからといって、質が高いとは限りません。資料請求をしたり、実際に足を運んだりして、信頼できるスクールなのか、講師の先生の熱心さはどうなのかといったことを見極めることが大事です。
「420時間日本語教師養成講座」の費用を抑える方法
40〜70万円の受講料がかかる「420時間日本語教師養成講座」ですが、交通費や昼食代、模擬授業の教材費など、それ以外にも経費がかかってくるものです。勉強を進めていくうちに、苦手を克服するためにオプション講座などを受けたくなるかもしれません。
そのため、できれば予算は多めに残しておきたいものです。できるだけ抑えられるものは抑えて、お金の心配はせずに勉強に打ち込めるようにしましょう。
民間資格「日本語教育能力検定試験」を独学で受験
多くの日本語教育機関では、民間資格である「日本語教育能力検定試験」に合格することが採用条件のひとつになっています。
そこで、独学で勉強して「日本語教育能力検定試験」を受験するという選択肢も考えてみましょう。独学であれば、養成講座に通わなくても日本語教師になることが可能です。
出費は、参考書や過去問などのテキスト代、受験費用17,000円(税込)のみとなるため、養成講座に通うのと比べると、出費はかなり抑えることができます。
費用面でメリットが大きい独学という方法ですが、もちろんデメリットもありますので、よく考えて決めましょう。
日本語教育能力検定試験について詳しくは以下の記事をご確認ください。
通信講座に通う
日本語教師養成講座には、通信講座もあり、通学と比べると5〜10万円程度安い講座もあります。安い理由は、通信講座ではeラーニングやオンライン授業がメインとなるので、実地の授業と比べると講師代などの経費を削減することができるからです。
なお、養成講座をオンラインで行う場合には、120単位以上の授業を対面、もしくは同時双方向で行うメディアで実施しなければならないルールがあるので、理論科目はオンラインで、教育実習は通学で行われるケースがほとんどです。
教育訓練給付支援制度を利用する
給付のための条件はありますが、厚生労働省が実施する教育訓練給付支援制度を利用する方法があります。この方法では、養成講座を修了後、ハローワークから受講料の20%(上限額10万円)が給付金として受け取れます。受講料が50万円以上であれば、上限の10万円が返ってくるわけです。
教育訓練給付金制度を利用するための条件は以下の4点です。
- 厚生労働大臣が指定した日本語教師養成講座であること。
- 雇用保険に3年以上加入していること(初めての支給の場合は1年以上)。
- 離職日の翌日から1年以内に受講を開始すること。
- 給付金を受けたことがある場合は、受講開始が前回の受給から3年以上経過していること。
※参照:『ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度』
(厚生労働省ホームページ・https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html)
求職者支援訓練を受ける
ハローワークの求職者支援制度のひとつである求職者支援訓練を受ける方法です。
再就職・転職をめざす人が、月10万円の給付金を受けながら、無料でさまざまな講座を受講できます。日本語教師養成講座を職業訓練として受講することができれば、費用は無料もしくは教材費のみとなります。
受給のための条件は下記の4点です。
- 原則として無職であること。
- 日本語教師として働く意思と能力があること。
- 雇用保険被保険者・雇用保険受給資格者でないこと。
- ハローワークに求職者として申し込みをしていること。
※参照:『求職者支援制度のご案内』(厚生労働省ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html)
受講料の安いスクールや割引制度を利用する
数は少ないのですが、スクールによっては日本語教師養成講座の受講料が安いところもあります。人気があるスクールは、価格帯が低くても授業や講師の質が高く、コストパフォーマンスがいいところもあります。
また、安いスクールを選ぶにはポイントがあります。
まず一つ目に、入学金・教材費・交通費を考慮すること。受講料は安くても、入学金や教材費は別で、実際はほかのスクールとあまり変わらないこともあります。見落とさないように注意しましょう。また、受講料が安くても、遠方で交通費がかさむ場合もあります。トータルの経費を考えるようにしましょう。
二つ目は、文部科学省への届出が受理されているスクールであるかどうか。届出が受理されていない養成講座を受講した場合、日本語教師の採用条件を満たせないことがあるので注意しましょう。
三つ目は、設立年度や修了生の人数を確認すること。スクールの実績は、質のよい授業内容や有利な就職活動につながります。
事前に確認しておきましょう。
さらに、さまざまな割引制度を取り入れているスクールもあります。数万円ではありますが、説明会や体験授業に参加することで、入学金が免除になる場合もあります。利用できる割引制度を調べて、活用するようにしましょう。
大学で日本語教育を学ぶ場合
大学で日本語教育を主専攻または副専攻し、日本語教師になるには4年間の通学が必要です。国立大学の場合は、入学金と4年間の授業料の合計が約240万円、私立大学では約400万円がかかります。これに加えて、交通費や昼食代、教科書代などの経費も必要です。さらに、希望する大学が遠方の場合は、住居費や水道光熱費も別途必要となります。
※参照:『国公私立大学の授業料等の推移』(文部科学省ホームページ・https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf)
安く抑えたい場合は通信制大学も検討
大学で日本語教師になる資格を取るためには、通学制よりも費用が安くて済む通信制大学という選択肢もあります。通学制と比べると、学費が半額以下で通えるところも多く、負担がかなり軽減されます。
また、通信制大学は授業料が安いばかりでなく、通学のための費用がかからず、自分の好きなタイミングで学修ができることもメリットです。そのため、社会人でも比較的学習しやすく、通勤中や昼休みにテキストを読むなど、すき間時間を活用した学修も可能です。
スクーリングで通学しなければならない大学もありますが、大学によってはスクーリングも含めてオンラインで完結する場合もあります。
例えば、大手前大学 通信教育部は、教育実習以外はオンラインで完結します。
国家資格「登録日本語教員」を独学で受験
2024年7月現在、大学で日本語教育を学べば、多くの日本語教育機関の採用条件のひとつである「大学または大学院にて日本語教育に関する教育課程を修了」はクリアできます。しかし、今後はその採用条件が「登録日本語教員資格が必要」となる可能性もないとは言い切れません。できれば、登録日本語教員資格を取得しておくほうが安心でしょう。
「登録日本語教員」の資格取得には、独学で受験できる試験ルートがあります。このルートでは、大学などの登録日本語教員養成機関に行くことなく、受験が可能です。
この場合、日本語教員試験の基礎試験と応用試験の両方を受ける必要があり、受験料は18,900円です。さらに、実践研修も必須で、受講にかかる費用(手数料)は50,900円と定められています。しかし、具体的な金額は文部科学大臣による認可によって決められるため、それぞれの登録日本語教育養成機関によって異なります。
「登録日本語教員」取得にかかる費用
登録日本語教員の資格を取得する際にかかる費用を解説します。
まず、必要となるのは、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の授業料です(現時点では正確な金額は不明)。
次に、日本語教員試験の基礎試験と応用試験の受験料が必要です。ただし、養成機関ルートのうち、登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する人は、基礎試験が免除となり、登録実践研修機関での実践研修の費用が必要となります。
養成ルートのうち、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する人は、基礎試験に加え、実践研修も養成課程と一体的に実施されているため実質的に免除となり、応用試験のみの費用が必要となります。
実践研修の受講にかかる費用(手数料)は50,900円と定められていますが、具体的な金額は文部科学大臣による認可によって決められるため、それぞれの登録実践研修機関によって異なります。
試験ルートでは、前述の通り、基礎試験、応用試験、登録実践研修機関での実践研修の費用が必要です。
また、現職の日本語教師が該当する「経過措置Cルート」でも、基礎試験と実践研修が免除されるため、応用試験の費用のみが必要です。
大手前大学 通信教育部は、「登録日本語教員資格の取得」で説明した「経過措置適用対象」となっている大学なので、「経過措置Cルート」で登録日本語教員をめざすことができます。
また、大手前大学は文部科学大臣の登録を受けた「実践研修と養成課程を一体的に実施する機関」をめざしています。※1
※1 文部科学省における審査の結果、予定した実践研修(又は養成課程)が開設できない可能性があります。
※参照『登録日本語教員の登録申請の手引き』(文化庁ホームページ・https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93982901_17.pdf)


※登録日本語教員の資格取得について詳しくは以下の記事をご確認ください。
「420時間日本語教師養成講座」や大学を選ぶ際のポイント
費用のことがわかってきたら、「420時間日本語教師養成講座」に通うのか、それとも大学へ進学するのかが見えてきたと思います。具体的に「420時間日本語教師養成講座」や大学を選ぶには、どんなことをポイントにすればよいのでしょう。
三つの大事なポイントを解説します。
目的や求めていることをクリアにする
自分が求めていることを明確にしましょう。価格の安さを重視するのか、それとも通いやすさを重視するのかだけでも、選択肢は違ってきます。
授業や講師の質はもちろん、就職のサポートが手厚いなど、講座や大学によって差があります。多少は高くても、それらを重視したいのか、そうではないのかを考えてみましょう。そうすれば、最終的な決断を下すときの迷いが少なくて済み、また入学してからも「価格よりも質で選んだのだから」「安い分、この足りない面は納得していたはず」と、余計なことを考えずに勉強に集中できるでしょう。
ライフスタイルに合わせて選ぶ
養成講座や大学には、通学形式と通信講座、通学と通信講座を組み合わせた三つのパターンがあります。その三つのなかから、勉強をする目的とライフスタイルに合ったパターンで通える講座や大学を選びましょう。
もちろん、対面での授業で実践的に力を付けたいのであれば通学形式になりますし、時間的に余裕がない人や、自分のペースで進めたい場合は、通学と通信を組み合わせた講座がいいでしょう。学び方のパターンによっては、期間が長くなったり、短くなったりすることもあるので、その点も考慮して選びましょう。
不明な点は訪問して確かめる
自分の価値観が明確になったら、あとは多くの養成講座や大学から自分の条件に合ったところを探し出すだけです。ホームページや資料請求などで確かめて、いくつかに絞り込んだ後は、実際に説明会などに参加するのがおすすめです。できれば、体験授業も受けて、授業の内容や雰囲気を体感しましょう。
体験授業がない場合は、スタッフに質問をして疑問点はクリアにしましょう。その際のチェックポイントは、カリキュラムの内容、就職活動へのサポート、講師やスタッフの対応などです。
最終的には通ってみなければわからないことですが、実際に足を運ぶことでわかることも多いはずです。また、複数のスクールや大学を見比べると、違いがわかることもあると思います。入学後の満足度を上げるために、事前の訪問をおすすめします。
まとめ

今回は、日本語教師養成講座の平均費用と、受講にかかる費用を安く抑えるコツについて解説しました。
これから養成講座を受講しようと考えている人は、教育訓練給付金制度や求職者支援制度を利用できないかどうかを、居住地のハローワークで確認してみることをおすすめします。スクールの割引制度も積極的に活用して、養成講座をできるだけリーズナブルに受講しましょう。
ここまで見てきたように、短期間で少ない費用で日本語教師の資格が取れる、独学や養成講座は魅力がありますが、その一方で、大学で学ぶという選択もあります。時間と費用をかけて大学で日本語教師をめざすのには、養成講座にはないメリットがあります。例えば、大手前大学 通信教育部であれば日本語教育に加え、ビジネス科目や心理学科目などから自由に選択して学べるカリキュラムを展開しております。
次では、大学で日本語教師の資格を取る魅力について解説します。
〈メリット1〉経過措置の適用により、最短2年※で国家資格取得の準備が完了!
日本語教員が登録日本語教員という国家資格になったことに伴い、文部科学大臣が一定の基準を満たすと認定した日本語教員養成課程を修了し、学士の学位を有する人には経過措置が適用されます。
この経過措置の適用が認められている通信制大学の日本語教員養成課程では、オンライン学修+教育実習で日本語教員に求められる必須の教育内容50項目を満たして修了した後、所定の試験に合格した上で登録申請すると、登録日本語教員の資格を取得できます。
※必修13単位を修得、在学2年目に日本語教育実習の単位を修得し、2年間で必修14単位(教育実習を含む)および選択必修2単位を含む27単位以上(うち日本語教育実習をのぞくスクーリングまたはメディア授業<ライブ型>5単位を含む)を修得した場合。
※入学時点で学士の学位を有していない場合は、最終学歴に応じて正科生として入学もしくは編入学し、大学を卒業する必要があります。
〈メリット2〉活躍の場は国内外!大学資格と同時取得でさらに活躍の場が広がる!
日本語教員の活躍の場は、国内外の日本語学校はもちろん、海外協力隊や国際イベント開催時のボランティアなど多数。国内でも、近年の訪日外国人、在留外国人の増加に伴い、需要が高まっているほか、同時に大卒資格を取ることで、大卒必須の企業の駐在日本語教員や日本語教育機関まで就職先を広げることもできます。
また、海外で働く際に「日本語の教育」という目的が明確な日本語教員は、比較的容易に就労ビザが取得できます。取得には大卒資格が条件となっているため、大卒資格を取得しておくことでより活躍の場を広げられます。
〈メリット3〉日本語教員に必要とされるスキルと同時に、幅広い知識を習得できる!
日本語教員は言語への理解はもちろん、日本に対する経済や文化などの幅広い知識や、多様性への理解も必要とされます。大学では、ビジネスや心理学、教養など日本語教員になるための必修科目以外も幅広く受講することが可能。幅広い知識を習得した日本語教師をめざせます。
大手前大学 通信教育部で日本語教師(登録日本語教員)をめざす
大手前大学 通信教育部は、「登録日本語教員資格の取得」で説明した「経過措置適用対象」となっている大学なので、「経過措置Cルート」で登録日本語教員をめざすことができます。
また、大手前大学は文部科学大臣の登録を受けた「実践研修と養成課程を一体的に実施する機関」をめざしています。※1
大手前大学で登録日本語教員をめざすメリットは、大学卒業資格も取得できることで、日本語教師としての活躍のフィールドが広がること、日本語教員養成課程のカリキュラムに加えて、170科目から興味ある科目を学べるので、日本語教師になってから役立つ教養・知識が習得できること、さらには、教育実習以外は24時間対応のオンライン学修で修了できることなどです。※2
※1 文部科学省における審査の結果、予定した実践研修(又は養成課程)が開設できない可能性があります。
※2 大手前大学で登録日本語教員の資格を取得する場合について、詳しくは以下の記事をご確認ください。
海外移住への第一歩として資格取得をめざしたHさん

日本語教員の資格を取得。
新たなキャリアのスタートに期待を膨らませています。
将来ベトナムに移住し民宿を経営したいと考えています。その実現のための第一歩として日本語教員の資格取得を決意。また就労ビザ取得のためには学士号が必要なので、日本語教員と学士号の両方をめざせる大手前大学を選びました。同時期に転職と進学が重なったのですが、オンライン受講が中心なので仕事と両立できると判断。動画授業の倍速視聴や科目試験のオンライン受験など、思っていた以上の学びやすさがあり、挫折することなく継続して勉強できたことは大きな自信になりました。日本語教育実習では、5日間みっちりと実践的な指導経験を積むことができました。特にティーチャートークといって、日本語学習初級者が理解しやすいような話し方や言葉選びを訓練できたことがよかったです。授業づくりも経験し、バックパッカーでの体験を取り入れた内容には生徒から「おもしろかった」と感想がもらえ、初めて教える喜びを噛み締めることができました。卒業後、日本語学校に内定をもらえたので、新たなキャリアのスタートに期待を膨らませています。
大卒資格とのW資格取得を目標に入学したTさんのケース

日本語教員としてのキャリアアップをめざし、
専門的に学べる通信制大学へ。
非常勤講師として日本語教員のキャリアをスタートさせるも、制度の見直しにより国内外で活躍するには大卒資格が欠かせないことを知りました。卒業率の高さなどに注目して大学を検討していたときに、先輩講師から「日本語教育に特化した大学ある」と紹介されたのが大手前大学でした。スクーリング科目を履修することなく、オンラインでの学修だけで卒業できることも入学の決め手になりました。印象的だったのは、先生方の指導方法でした。話し方や間のとり方、教材など学修意欲を高めるためのさまざまな工夫があり、一方的に教わるのではなく、学生が能動的に考え、理解が深まる授業でした。自分が体験した学修を通して発見した学ぶ楽しさを日本語教員の指導にぜひ活かしたいと思います。
仕事や家事と両立して卒業したWさんのケース

“学びたい、知りたい”と思ったら行動する!
大手前の学びが生涯学習の基盤になりました。
ドイツ人の夫と生活をしていると、「気を付けてね」の「ね」ってどういう意味といった、日本語に関する質問をよく受けます。私自身も答えに詰まることが多く、自分で調べていくうちに、日本語教育に興味を持ちました。大手前大学を選んだ理由は、自分のライフスタイルに合わせて学修できるeラーニングや、専攻に関係なく興味がある分野を学ぶことのできる履修制度に魅力を感じたからです。実際に履修してみると、教科の達成度がパーセンテージで表示されるため状況を把握しやすく、仕事や家事と両立しながらでも学修計画通りに進めることができました。また、日本語教育能力検定試験対策ができる科目もあり、無事に合格することができました。行き詰まることもありましたが、熱心な指導と細やかなサポートのおかげで卒業時には優等賞を受賞することができました。”知りたい”という気持ちと、好奇心を大切にして、一生涯、学び続けたいと思います。将来は、日本語や食文化を通して日本の魅力を伝えていきたいです。